⚠重要⚠ ネットワーク障害について
こんにちは!院長の松前です。本日6月9日(月)16:00現在、弊社においてNTTのネットワーク障害が発生しておりお電話がつながらない状態となっております。
復旧の見込みが木曜日頃になっております。
その間にお問い合わせがある方は恐れ入りますが、公式LINEより問い合わせを頂ければ幸いです。
ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ボディケアサロンM’s
院長 松前 克俊
神奈川県横浜市のボディケアサロンM'sでは、慢性的な腰痛や肩こりにストレッチと鍼灸治療を組み合わせた施術をご提供しております。
ホーム ≫ M'sブログ ≫

こんにちは!
「寝つきが悪い…」「疲れているのに眠れない…」
そんな夜はありませんか?
実は、体の緊張が残っていると自律神経が切り替わらず、
睡眠の質が下がることも。
そこでオススメなのが、寝る前たった1分のストレッチ!
忙しい方でも取り入れやすい、簡単ケアをご紹介します☆
1,深呼吸+首ストレッチ(20秒)
・鼻からゆっくり吸って、吐きながら首を左右に倒す(交互に行う)
首の横~肩がじんわり伸びるのを感じましょう◎
2,肩甲骨まわし(20秒)
・両肩を耳に近づけるようにすくめて、後ろに大きく回す×5回位
巻き肩、猫背が緩むと、呼吸もしやすくなります◎
3,ひざ抱えストレッチ(20秒)
・仰向けで両膝を手で抱え、体をゆらゆら動かす
腰まわり、お尻、太もも裏がほぐれて緊張が緩和します◎
たった1分でも、続けると
体と心のスイッチが切り替わりやすくなります!
体が疲れているサインを放っておかず、忙しい日々でも、
少しだけ自分自身と向き合う時間を作れると気分も晴れます。
是非、゛1分だけ゛取り入れてみてくださいね(^^)
横浜のストレッチ、鍼灸マッサージ・整体、産後骨盤矯正なら港南区にあるボディケアサロンM'sへ☆
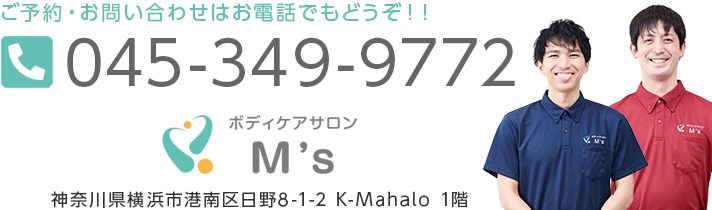

こんにちは!
新年度が始まって、バタバタと過ぎた4月。
少しずつ気温も上がって、気が付けばもうすぐゴールデンウィークですね☆
旅行やレジャー、帰省やおうちでのんびり過ごす方も、、
もう予定は決まりましたか??
この時期は新生活で疲れが溜まりやすく、
実はカラダが少しお疲れモードになっている方が多いです。
そんな゛不調゛をそのままにしておくと、
せっかくの連休中も疲れやすくなってしまうことも。
ストレッチで、優しく体をゆるめてあげることで
「動きやすい」「疲れにくい」状態へ
旅行やレジャーの前に、メンテナンスしておくのがオススメです♪
当サロンでは、お一人おひとりの状態に合わせて
じっくりとストレッチをして、整えていきます。
是非、今まで感じたことのない体がスッキリする感覚を味わってみてください!
横浜のストレッチ、鍼灸マッサージ・整体、産後骨盤矯正なら港南区にあるボディケアサロンM'sへ☆
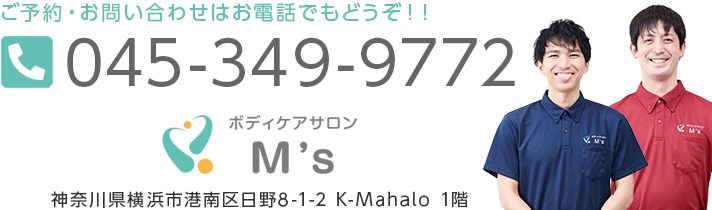
こんにちは!院長の松前です。
7年5月3日(土)~5月5日(月)の間、休業とさせていただきます。
お客様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。
横浜のストレッチ、鍼灸マッサージ・整体、産後骨盤矯正なら港南区にあるボディケアサロンM'sへ☆
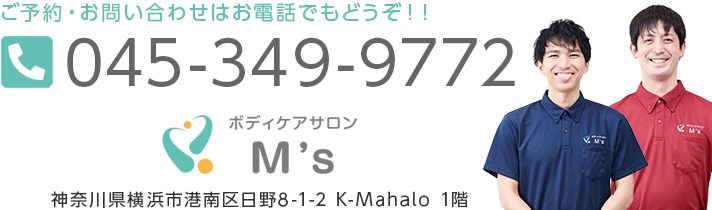

こんにちは!
最近、こんな体調の変化を感じることはありませんか?
・朝起きるのがしんどい
・頭がぼーっとする
・気分が上がらない
・なんとなくイライラする
・夜になってもなかなか寝付けない
これ、実は全て 「春の自律神経疲れ」 が関係しているかもしれません。
春はぽかぽか陽気のはずが、昼は温かいのに朝晩はひんやり。
日によっては真冬のような気温に戻ることもあります、、
こうした気温差や気圧の変化は、私たちの体にとってはストレス。
さらに4月は、入学・進学・転勤・新年度…と 『環境の変化』 も多く、
知らず知らずのうちに自律神経が疲れてしまいやすいのです。
☆今日からできるセルフケア
1,首・肩を優しくストレッチ
お風呂上がりに、首をぐるぐる回したり、肩をすくめてストンと落とすだけでもOK。
筋肉が緩むと、神経も緩みリラックスできます◎
2,自律神経を休ませるツボ押し
・内関(ないかん):手首の内側〈ストレス・不安にも効果的〉
・神門(しんもん):小指側の手首のしわ上〈緊張や不眠に〉
・太衝(たいしょう):足の親指と人差し指の間をなぞって止まるくぼみ
指で気持ち良い程度に5~10秒押してみてください◎
3,首の後ろを温める
ホットタオルや湯たんぽで首の付け根をじんわり温めると、
副交感神経が優位になりやすくなります。
リラックスして眠りやすくなるので、夜寝る前にもおすすめ。
ぜひ、今日から試してみてください◎
「なんとなく不調だけど、病院に行くほどじゃない」
そんな声を多く聞く季節です。
実は、その違和感こそが、体からのSOSのサインです。
小さなうちにケアをすることで、体も心もぐっと楽になります。
私たちも、何か力になれることがあるかもしれません。
ぜひ、溜め込まずお気軽にご相談ください(^^)
横浜のストレッチ、鍼灸マッサージ・整体、産後骨盤矯正なら港南区にあるボディケアサロンM'sへ☆
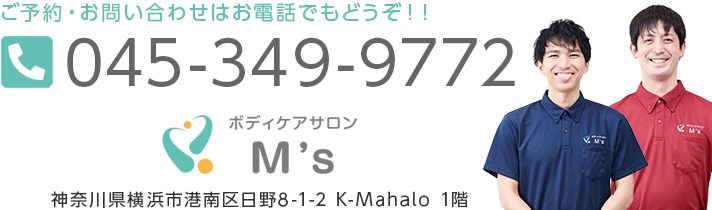

こんにちは!
もうすぐ3月も終わり、本当にあっという間に4月ですね。
そろそろ桜も見頃を迎えるころではないでしょうか?
そんな春は、冬の間に溜め込んだ老廃物をデトックスし、
心身をリフレッシュするのにぴったりの季節です!
東洋医学では、「肝」の働きが活発になる時期とされています。
「肝」は血を蓄え、全身に巡らせる役割があり、解毒やストレス管理とも関係が深い臓器です。
しかし、春は気温差が大きく、自律神経が乱れやすい時期でもあるため、
「肝」の働きを助ける食事を意識することが大切です。
今回は、春の不調を防ぎ、エネルギーを巡らせる食養生についてご紹介します!
☆春の食養生のポイント
1,酸味のある食材で「肝」をサポート
酸味には、肝のエネルギーをスムーズに巡らせる作用があります。
◎レモン、グレープフルーツ、オレンジ、梅干し、お酢
2,デトックスを促す春の旬食材を摂る
老廃物を排出するため、デトックス作用のある野菜を積極的に摂りましょう。
◎山菜、菜の花、キャベツ、小松菜、ほうれん草、ゴボウ、レンコン
3,胃腸を整える発酵食品を取り入れる
肝がスムーズに働くには、胃腸の調子を整えることも大切です。
◎味噌、納豆、ぬか漬け、ヨーグルト、キムチ
4,エネルギー不足を防ぐたんぱく質&鉄分補給
エネルギー不足が原因で、眠気やだるさを感じることも、、
◎鶏肉、卵、豆腐、レバー、ひじき、貝類
春は新しい環境や気候の変化で体調を崩しやすい時期ですが、
食事を工夫することで不調を防ぐことができます。
酸味のある食材や旬の野菜を取り入れ、体の内側から整えていきましょう!
ぜひ、今日の食事から少しずつ意識してみてくださいね !(^^)!
横浜のストレッチ、鍼灸マッサージ・整体、産後骨盤矯正なら港南区にあるボディケアサロンM'sへ☆
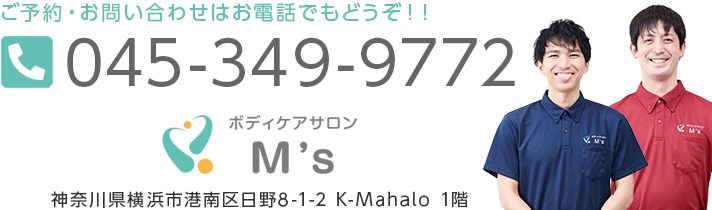

こんにちは!
院長の松前です。
2月に入社し、研修を重ねてきた中村優菜先生が今週3月15日(土)にデビューします!
前職の整骨院でもストレッチや筋膜リリースを担当していたため、入社時からしっかりとした技術が身についておりましたが、
さらにレベルアップし、ついにデビューとなります♪
ぜひ優菜先生の施術をご体感ください♪
デビューキャンペーンも行っております☆
詳細は公式LINEに登録の上、お問い合わせください☆
お問合せお待ちしております!
横浜のストレッチ、鍼灸マッサージ・整体、産後骨盤矯正なら港南区にあるボディケアサロンM'sへ☆
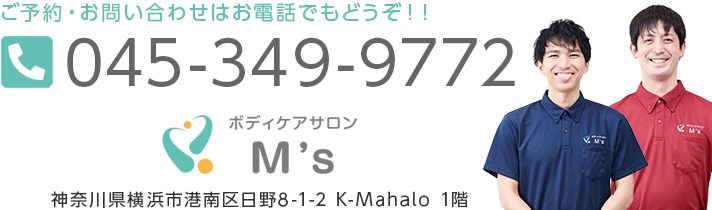
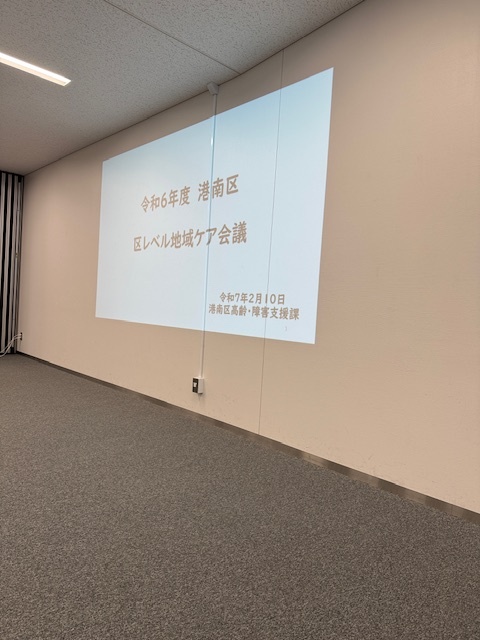
こんにちは!
院長の松前です。
先日港南区役所で行われた地域ケア会議に出席してきました。
当院は港南区が独自に行っている【見守り事業所】に登録しており、今回はその一環で未認知症の方を地域でどのように見守っていくかというテーマの会議でした。
当日はクリニック、歯科、薬局、高齢者施設、美容室などなど、、、数えきれない業種の方々が参加され、総勢60名くらいはいたのではないでしょうか??
とても有意義な時間となりました。
これからも地域に根差し、社会に必要とされる会社を目指して進んでいきたいと思います。
当日ご参加された皆様ありがとうございました!
横浜のストレッチ、鍼灸マッサージ・整体、産後骨盤矯正なら港南区にあるボディケアサロンM'sへ☆
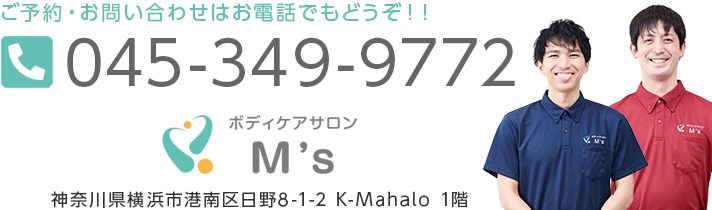

こんにちは!院長の松前です。
最近呼吸が浅く、身体の調子を崩してしまっている患者様が多いように感じます。
そのため、今回は呼吸筋についてご紹介します。
肺は胸郭という肋骨で覆われた部屋に取り囲まれていて、この胸郭が広がることで空気が入り、胸郭が狭くなることで空気が出ていきます。
こうした胸郭の拡大や収縮を起こすのが、胸郭のまわりの筋肉です。 このように胸郭を動かし、呼吸に関わる筋肉のことを「呼吸筋」といいます。
呼吸筋の働き
このように呼吸数が増加するため、定期的な運動は呼吸筋の強化につながります
【姿勢を改善する】
姿勢と呼吸は密接に関係しており、姿勢が悪いと呼吸が浅くなり、呼吸が浅いと姿勢が崩れる可能性があります。
猫背はただ姿勢が悪く見えるというだけでなく、呼吸にも大きな影響を与えます。
不良な姿勢が長く続くと、胸郭の可動域が狭まり、肺の膨張が十分に行われず、呼吸が浅くなる傾向があります。
これは、呼吸に必要な酸素の取り込みが減少することを意味し、疲労感やストレスの増加に繋がってしまいます。
また胸郭の動きが悪くなることで、腰椎の前後屈への制限もかかり腰痛の原因となって暇う場合もございます。
当院では呼吸に関わる筋肉のストレッチはもちろんのこと、脊柱際の凝り固まった筋肉への徒手療法、腹部を押圧しながらの腹式呼吸トレーニングなど、様々なバリエーションの施術を患者様に合わせて行っております。
「なかなか疲れが取れない」、「不眠に悩んでいる」などございましたら、一度呼吸を見直しに当院にお越しください☆
皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております♪
横浜のストレッチ、鍼灸マッサージ・整体、産後骨盤矯正なら港南区にあるボディケアサロンM'sへ☆
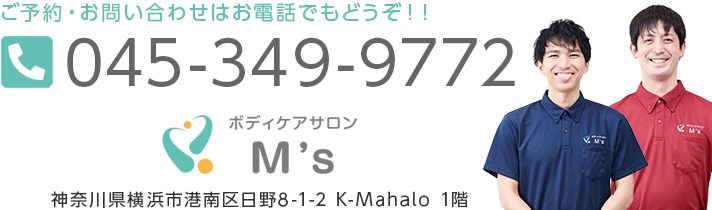
こんにちは!院長の松前です。
あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い致します
皆様はどのような年末年始でしたか?
私は年末スキー、年明けはハワイアンズへ!
、、という予定だったのですが、息子が体調が万全でなかったため近場でゆっくりと過ごすお正月となりました。
それでも一日家にいることは苦手なので、川崎にあるスポッチャや三浦のソレイユの丘などで楽しませて頂きました♪
本年も患者様の少しでもお力になれるようスタッフ一同一生懸命施術をさせて頂きます!
よろしくお願い致します。
横浜のストレッチ、鍼灸マッサージ、産後骨盤矯正なら港南区にあるボディケアサロンM'sへ☆
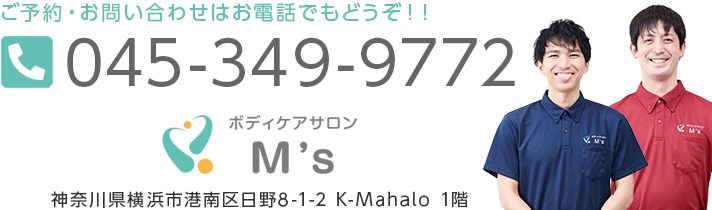
〒234-0051 神奈川県横浜市港南区日野8-1-2
K-Mahalo 1階
月~金10:00~19:30
(最終受付18:30)
土曜日9:00~18:30
(最終受付17:30)
日曜日定休
スマートフォンからのアクセスはこちら